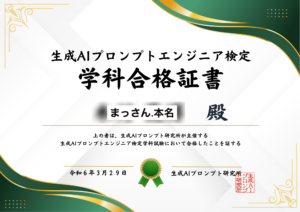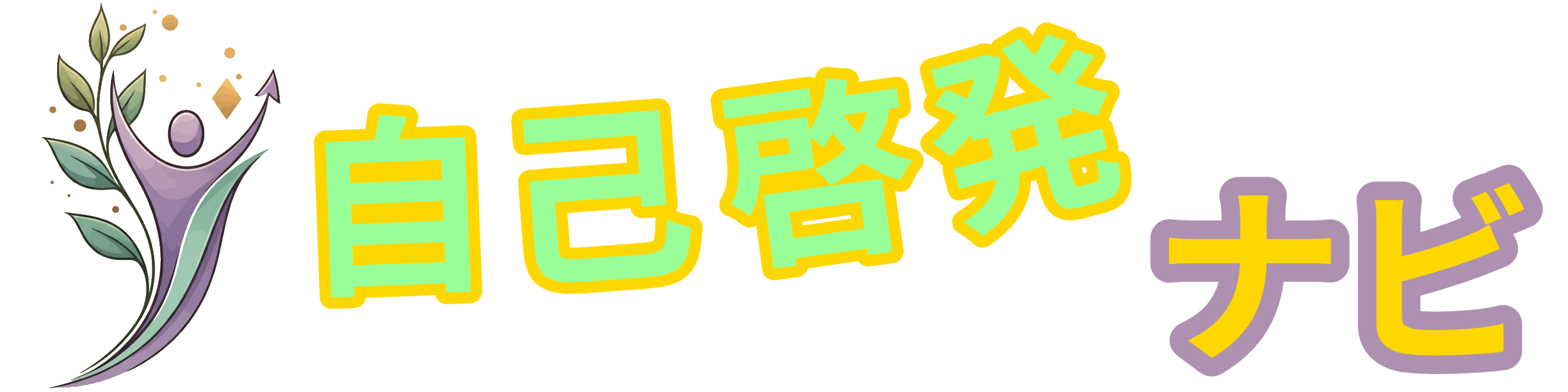こんにちは、生成AI使いのまっさん.です。
※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
それではごゆっくりとご覧ください。
2025年春に大流行した
「ジブリ風で画像を作って」
「自分をディズニー風にして」
というのを覚えていますか?
SNSを見ていて
「プロフィール画像をアニメ風に変えた友人を何人も見かけた」
という体験をされた方も多いのではないでしょうか?
実は、多くの人が「楽しい思い出」として振り返るあの大流行の中に、深刻な法的リスクが潜んでいたのです。
私は2024年11月に生成AIパスポート試験に合格し、AI著作権については「気をつけなければいけないなぁ」と漠然と意識していました。
そんな中で迎えた2025年春の大流行。SNSがジブリ風・ディズニー風の画像であふれる様子を見ながら、「盛り上がっているけれど、著作権的に大丈夫なのかな?」と気になっていました。しかし、明確な根拠もなく、結局何もアクションを起こすことなく静観していました。

その後、改めてAI著作権について詳しく学び直してみると、あの流行がいかに法的にリスクの高いものだったかがよく分かりました。「あの時、なぜもっと積極的に注意喚起できなかったのだろう」という反省も込めて、この記事では私が学んだ具体的なリスクと対策をお伝えします。
「知らなかった」では済まされない法的リスクを回避し、安心してAIを活用するための完全ガイドです。
最終更新:2025年10月9日
2025年春の大流行で何が起きていたのか
ジブリ風・ディズニー風加工の社会現象
2025年3月、OpenAIがChatGPTの画像生成機能を無料開放すると、SNSは一夜にして「アニメ風プロフィール画像」であふれかえりました。
流行の規模がすごかった
- 機能公開後1時間で100万人が新規登録
- OpenAIのCEOサム・アルトマンが自身のプロフィール画像をジブリ風に変更
- Y Combinatorやスタートアップ関係者から一般ユーザーまで爆発的に拡散
みんなが試していた指定例
「ジブリ風で」
「ディズニー風にして」
「ドラゴンボール風で作って」
「アニメキャラクター風に変換して」
あなたも友人のSNSで、こうした画像を何度も目にしたと思います。当時は「すごい時代になったね!」と感動していたかもしれませんね。
しかし、法的な観点から見ると…
実は、この行為には重大な著作権侵害リスクが潜んでいました。
法的な観点から、なぜ危険だったのかを見ていきましょう。
依拠性の明確な証拠
著作権侵害が成立するには「類似性」と「依拠性」の両方が必要です。
「ジブリ風で」「ディズニー風で」という指定は、既存の著作物への明確な参照を示します。これにより、著作権侵害の要件である「依拠性」が容易に立証されてしまいます。
個人の楽しみから商用利用への危険な展開
流行の初期は個人の趣味の範囲でしたが、次第に以下のような用途で使用される例が増えました:
- ビジネス用プロフィール画像での使用
- 商品・サービスの宣伝材料への転用
- 有料コンテンツでの無断使用
- クライアントワークでの納品物への流用
デジタル証拠の残存
AIサービスの多くはプロンプト履歴を保存しており、これが法的証拠として使用される可能性があります。「○○風で作って」という指示は、裁判において決定的な証拠となりうるのです。
その他の危険な流行パターン
ジブリ風以外にも、同時期に流行した以下のパターンも同様のリスクを伴っていました:
キャラクター系
× 「ミッキーマウス風で」
× 「ポケモン風のキャラクター」
× 「ドラえもん風にして」
漫画・アニメ作家系
× 「鳥山明風の絵で」
× 「尾田栄一郎風のイラスト」
× 「宮崎駿監督風の背景」
文章生成でも同様の問題
× 「村上春樹風の小説を書いて」
× 「スティーブ・ジョブズ風のプレゼン原稿を作成して」
× 「○○監督風の脚本を生成して」
当時「みんなやってるから大丈夫」と思っていた行為が、実は法的にグレーゾーン、場合によっては完全にアウトだったのです。もしかすると、思い当たることがあるかもしれませんね。
こうしたAI著作権問題について、実は多くの人が知らない専門的な議論もあります。
専門家が警鐘を鳴らす「生成AIツール論」の法的リスク
流行の最中、一部で「生成AIはペンや絵の具と同じ道具だから問題ない」という「生成AIツール論」が語られていました。しかし、AI著作権問題の専門家の間では、この考え方に重大な誤解が含まれており、実務上極めて危険であると指摘されています。
法律専門家が注意する「ツール論」とは
典型的な主張
「生成AIはペンや絵の具と同じ道具だから、プロンプトを入力した人に著作権がある」
この論理に基づいて、AI生成物を自分の著作物として商用利用したり、他者に権利を主張したりするケースが増えていますが、法的根拠が薄い危険な行為です。
法的現実との深刻な乖離
米国著作権局の明確な見解(2025年)
「AIによって完全に生成されたコンテンツは著作権保護の対象にならない」「プロンプトだけでは著作権を取得するには不十分」と明言されています。
日本の文化庁の見解
生成AIの成果物については「人間による創作性の有無」を慎重に検討する必要があるとされており、単純なプロンプト入力では著作権発生の可能性は極めて低いとされています。
実際の著作権発生条件
現行の法制度では、以下のように整理されています:
1. AI完全生成物
→ 著作権なし(パブリックドメイン状態)
2. 人間の創作的編集あり
→ 編集部分のみ著作権発生の可能性
3. 単純なプロンプト入力
→ 著作権発生の可能性は極めて低い
「ツール論」への依存が危険な理由
ビジネス上のトラブル
- 契約での権利主張で問題となる可能性
- クライアントとの認識齟齬
- 権利の二重譲渡問題
法的リスクの誤認
- 他者の著作権を侵害していないという保証にはならない
- 自分に著作権があるという主張の根拠としては不十分
- 訴訟時の立証責任で不利になる可能性
特に、2025年春の流行時に「ツール論」を根拠に商用利用された方は、専門家からは今からでも適切な対策を検討した方が良いとされています。
責任の所在:誰がリスクを負うのか
「それじゃあ、AI生成で著作権問題が起きた場合、全部自分の責任になっちゃうの?」
これは多くの方が感じる自然な疑問です。AI著作権問題における責任の所在は、実は想像以上に複雑なのです。
実際の責任分担を理解するために、まず重要な法的概念を見ていきましょう。
AIサービス提供者が責任を負うケース
学習データの問題
- 学習データの権利処理に問題がある場合
- 著作権侵害を助長する機能を提供した場合
- 適切な注意喚起を怠った場合
規範的行為主体論
AIが高頻度で著作権侵害物を生成する場合、提供者が規範的行為主体として責任を負う可能性があります。
規範的行為主体論とは?
これは、実際に行為を行った者ではなく、その行為を実質的にコントロールしている者が法的責任を負うべきという考え方です。AI著作権問題においては、例えばAIシステムが意図的に著作権侵害を助長するよう設計されている場合、実際の利用者よりもシステム提供者により重い責任があるとする論理です。
ユーザーが責任を負うケース
明確な指定をした場合
- 「○○風で」「△△のスタイルで」などの具体的指定
- 既存作品を意識した生成指示
- 類似性を認識しながら商用利用した場合
利用規約による責任の明記
多くのAIサービスでは、利用規約において生成物の使用責任をユーザーに帰属させています。つまり、「何か問題があってもユーザーの責任ですよ」という建付けです。
利用規約には効力の限界があります
法的責任の所在は、利用規約だけでは決まりません。特に重要なポイントがあります。
提供者が規範的行為主体として責任を負う場合がある
AIシステム自体に問題がある場合や、侵害を助長する設計になっている場合は、提供者側に責任が発生する可能性があります。
それでも、ユーザーの責任が完全に免除されるわけではない
仮に提供者が責任を負うことになっても、利用者側のリスクが完全になくなるわけではないとされています。多くの場合、両者が状況に応じて責任を分担することになります。
実際の責任分担
- 提供者の責任:システム設計、学習データ、侵害助長への責任
- ユーザーの責任:明確な侵害意図、商用利用での注意義務違反
- 共同責任:多くの場合、両者が程度に応じて責任を分担
つまり、AIサービス提供者が責任を負う場合でも、利用者側のリスクが完全になくなるわけではないとされています。
2025年春流行時の実際の状況
当時の状況を振り返ると:
- OpenAIは著作権リスクを意識し、特定のアーティストの模倣を制限していたが、スタジオ単位での規制はなかった
- その結果、ジブリ風の画像が大量に生成される事態となった
契約による責任分散の重要性
実務では、契約や利用規約による責任分担の明確化が最も重要です:
推奨される対応
- 使用前の利用規約徹底確認
- 不明な点の事前問い合わせ
- 商用利用時の法務担当者相談
- 適切な免責条項の設定
特に、ビジネスでAIを活用する際は、著作権問題以外にも多くの配慮が必要です。詳細はChatGPT使い方ビジネス完全ガイドで詳しく解説しています。
これらの複雑な問題を体系的に学ぶ方法
「2025年春の流行時は楽しくて何も考えずに使っていたけど、これだけ複雑な問題があるなんて知らなかった」とあなたも感じられたかもしれません。
実際、AI著作権問題は非常に複雑で、日常的なAI活用において適切な判断をするためには、断片的な知識ではなく体系的な理解が不可欠です。
基礎知識から実践まで:段階的学習のススメ
第1段階:基礎的な法的知識の習得
- 著作権の基本概念(著作物の定義、権利の種類)
- AI特有の法的課題の理解
- 国内外の法的動向の把握
第2段階:実践的な判断基準の習得
- 具体的ケースでの適用方法
- リスク評価の手法
- 予防策の実装方法
第3段階:最新動向への対応力育成
- 法改正への対応
- 技術進歩に伴う新たな課題への対処
- 専門家ネットワークの構築
私がAI著作権問題を意識するようになった学習体験
私自身、AI著作権問題を意識するようになったのは、生成AIパスポート試験の学習がきっかけでした。この試験を通じて、これらの複雑な問題について意識を高め、基本的な判断基準を身につけてきています。
生成AIパスポートで学べること
この試験はAI著作権問題だけを扱うものではありません。むしろ、生成AI活用における総合的なリテラシーを身につけることで、著作権を含む様々な課題に対処する基盤を構築できます:
- AI技術の仕組みと限界の理解
- 法的・倫理的課題への意識向上
- ビジネス現場での注意点の把握
- 継続的な学習の重要性の認識
私はこれらの知識を生成AIパスポート試験の学習で身につけてきました。このような基盤があることで、新しいAIツールが登場した時や、ビジネスでAIを活用する時、さらには日常的にAIを使用する際にも、適切に判断できるようになったと感じています。
生成AI活用の総合リテラシーを身につける学習リソース
著作権問題の重要性は理解していただけたと思いますが、実は生成AI活用にはもっと幅広い注意点があります。プライバシー、セキュリティ、倫理的配慮、ビジネスリスクなど、著作権だけでは語り尽くせない課題が存在するのです。
あなたが安全で効果的にAIを活用するためには、これらの課題について総合的な視点で学習することが重要です。そこで、私が実際に活用した効果的なリソースをご紹介します。
生成AIパスポート公式テキストで体系的に学ぶ
体系的な知識を身につけるために、私が実際に使った公式テキストをご紹介しますね。
この公式テキストは全7章構成で、AI技術の基礎から実践的なプロンプト技術まで幅広くカバーしています。特にAI著作権問題に関連する重要な内容として、以下の章が役立ちました:
第4章:インターネットリテラシーと権利関係
- 制作物に関わる権利と法律上の規制
- AI著作権問題のメカニズムと具体的事例
- 個人情報保護とプライバシー配慮
第5章:AIに関する基本理念・社会原則・ガイドライン
- AI社会原則の理解
- 共通の指針とガイドライン
- 倫理的なAI活用の考え方
私の経験では、AI著作権問題を単独で学習するよりも、このような総合的なアプローチの方が、実際のAI活用現場で適切な判断ができるようになると思います。
無料GPTで理解度をチェック
公式テキストで学んだ内容の理解度確認には、以下のGPTが効果的です:
(ChatGPTのアプリをインストールするか問われることがあります。インストールしたくない場合は、右クリックからリンクを開いてください。)
これらのGPTでは、生成AIパスポートのシラバスに沿った問題演習ができます:
- 章別の重点的な問題演習(「4章の問題を出して」など)
- 試験形式での理解度チェック
- 間違えやすいポイントの確認
- 学習の定着度測定
積極的なAI活用のためのプロンプト技術を学ぶ
ここまでは生成AI活用の「守り」の部分 ー リスク管理やコンプライアンスについて解説してきました。しかし、守りを意識しすぎて萎縮し、生成AIの可能性を活かしきれないのももったいないことです。
安全性を確保した上で、生成AIをより積極的に活用するための「攻め」の技術も身につけましょう。この記事のこれより先では、著作権リスクを回避しながら効果的にAIを活用するための具体的なプロンプト設計方法について解説しています。
適切な知識で「守り」を固めつつ、プロンプトエンジニアリングで「攻め」の活用法を身につけることで、あなたの生成AI活用はより安全で効果的なものになります。
もしあなたが著作権リスクを適切に管理しながら、生成AIを業務で本格的に活用していきたいなら、生成AIスクールで法的側面も含めた実践的なカリキュラムを受講することも検討してみてください。実際の判例や業界事例を交えた専門的な指導により、「グレーゾーン」での判断力を養うことができます。
安全なAI活用のための実践的チェックリスト
2025年春の経験を踏まえ、今後安全にAIを活用するための具体的なチェックリストをご提供します。
事前確認項目
AIサービスの利用規約確認
- 生成物の商用利用可否
- 著作権の帰属に関する規定
- サービス提供者の免責事項
- 責任分担の明確化
プロンプト設計での注意
- 特定の著作物名を含めない
- 「○○風のイラスト」ではなく「ファンタジー調のイラスト」
- 特定のキャラクター名や作品名の直接指定を避ける
- スタイル指定も一般的な表現に留める
使用目的の明確化
- 個人利用か商用利用かを明確に区分
- 商用利用の場合は追加の法的確認
- クライアントワークでの事前説明準備
生成中・生成後の確認項目
複数パターンでの検証
- 一度の生成結果に依存しない
- 異なるプロンプトでの複数生成
- 人間による創作的判断の各段階での介入
類似性の詳細チェック
- 既存の著作物との類似度確認
- 商標やロゴの意図しない生成確認
- 人物の肖像権侵害の可能性チェック
- 専門的なツールを用いた類似度検証
段階的な品質向上
- 基本的な構造から詳細への段階的生成
- 最終的な人による編集・調整
- オリジナリティの付加
商用利用時の特別注意事項
クライアントワークでの配慮
- AI使用の事前説明と同意取得
- 生成物の権利関係の明確化
- 修正・変更権限の事前合意
- 適切なクレジット表記の実施
社内利用でのガバナンス
- 社内ガイドラインの策定
- 従業員向けの研修実施
- 定期的な運用見直し
- リスク管理体制の構築
なお、AI著作権問題への理解を深めた上で、生成AIを活用した副業に興味がある方は、生成AI副業で稼ぐ方法と注意点で具体的な収益化方法を紹介しています。
2025年春の経験者向け特別チェック
過去生成物の見直し
- 当時作成した画像の使用状況確認
- 商用転用していないかの点検
- プロフィール画像等の適切な変更検討
学習機会の活用
- 今回の経験を教訓とした社内共有
- より安全な代替手段の検討
- 継続的な法的動向の把握
新たな論点:プロンプトの著作権について
AI著作権問題は日々進化しており、最近ではプロンプト自体の著作権という新しい論点も議論され始めています。
2025年春の流行時、効果的なプロンプトがSNSで共有されることも多かったのですが、実はここにも注意点があります。
注意すべきポイント
- プロンプト自体に著作権が発生する可能性がある
- 商用利用時は出典やライセンスの確認が重要
- 配布者との権利関係を事前に明確化する
現時点での対応
現在はまだ法的見解が定まっていない分野ですが、専門家からは安全のため以下の対応をしておいた方が良いとされています:
- 出典が不明なプロンプトの商用利用は避ける
- 可能な限りプロンプト作成者の許可を得る
- 自作プロンプトの開発スキルを向上させる
特に自作プロンプトのスキル向上については、生成AIセミナーのおすすめ情報で体系的な学習方法を紹介していますので、ご参照ください。
この分野の法的議論が進展次第、詳細な解説記事も検討していこうと思います。
よくある質問(FAQ)
AIが生成した画像や文章に著作権はありますか?
現行の法律では、AIが自動生成したコンテンツは原則として著作権が認められません。ただし、人間が創作的に編集・加工した部分には著作権が発生する可能性があります。
なぜAI生成物には著作権がないとされるのですか?
著作権は「人間の創作的活動」を前提としています。AIが自動的に作成したものは人間の創作性が認められないため、著作権保護の対象外とされています。
「ジブリ風」や「ディズニー風」と指定して生成するのは違法ですか?
既存の著作物やキャラクターを明示的に参照した生成は、著作権侵害と認定されるリスクが高いです。個人利用でも商用利用でも注意が必要です。
AIで作ったイラストや画像を商用利用できますか?
商用利用は特に注意が必要です。利用規約や著作権法に反していないか確認し、必要であれば法務担当や弁護士に相談しましょう。詳細はClaudeとChatGPT比較記事でも触れています。
AI小説やAI動画の著作権はどうなりますか?
小説や動画でも同様に、AIが自動生成しただけでは著作権は発生しません。人間がストーリー構成や編集で創作性を加えた部分に限定して著作権が認められる可能性があります。
プロンプト(指示文)に著作権はありますか?
短い指示文は著作権が認められにくいですが、独創的で具体的なプロンプトは著作権保護の対象になる可能性があります。商用利用時は出典やライセンスの確認が重要です。
AI著作権問題について体系的に学ぶにはどうすればいいですか?
文化庁の見解や各国の法制度を定期的にチェックするのが基本です。加えて、AI倫理ガイドラインの記事や、実践的に学べる生成AIセミナーもおすすめです。
生成画像や動画に「実在ロゴ/商標」が写り込んだら違法ですか?
文脈次第ですが、出所の混同を招く表示や、商標の信用を損なう使い方は商標法/不正競争防止法上のリスクがあります。
SNSでの「公式風」表現や商品化・広告転用は特に注意が必要です。
実務対応としては、
(1)ロゴの除去・マスク
(2)商品然と見える演出の回避
(3)商用時の社内審査と法務相談
を推奨します。
2025年秋の新事例:フィギュア風生成とSora動画の著作権・商標リスク
2025年9月以降、SNS上で「フィギュア風」生成画像に実在ブランドのロゴや企業シンボルが紛れ込む事例が拡大し、商標・不正競争の観点から注意喚起が相次ぎました。また、OpenAIの動画生成アプリ「Sora v2」では、日本の人気キャラクターに酷似する動画が多数出回り、権利者対応や政策論議が加速しています。
1. フィギュア風生成 × ロゴ・商標のリスク
何が問題になるのか
- 商標法:出所混同(「これは公式商品では?」と誤認させる)を招くおそれ
- 不正競争防止法:他人の著名表示を使用し、混同を生じさせる行為のリスク
- 信用毀損:暴力・差別表現等と結び付くと企業ブランドの毀損に直結
直近の公式アナウンス
- バンダイ/BANDAI SPIRITSがロゴ入り生成画像の拡散に注意喚起(「弊社商品ではない」)
参考:各社の公式サイトや主要メディアの情報を末尾に掲示
安全に楽しむための実務ガイド
- ロゴ・商標は写り込ませない(衣装タグ、台座刻印、箱パッケージ風表示なども注意)
- 「公式風の誤解」を招く構図・文言(#公式、発売決定…)を避ける
- 商用・広告利用は社内チェック+法務相談を徹底
2. Sora v2のキャラクター生成問題(動画)
9月末の公開直後から、著名IPに酷似する動画が拡散。OpenAIは方針を見直し、権利者がより細かく制御できる仕組み(グラニュラリティ向上)の導入を発表しました。日本の人気キャラクターを巡る懸念も多く報じられ、任天堂は「政府ロビー」報道を否定しつつ、知財保護の基本姿勢を表明しています。
現場での実務ポイント(動画)
- 固有名やシリーズ名をプロンプトに入れない(類似性+依拠性の立証リスクを下げる)
- 社内ガイドライン:公開前に第三者チェック(既存IP・ロゴ・人物肖像の混入確認)
- 生成後はフレーム単位でロゴ/特徴的造形を確認し、必要ならカット・マスク・差し替え
3. 政策・行政の動き(日本)
文化庁は継続的に生成AIと著作権の整理を進め、最新資料では関係省庁のガイドライン統合や法制度の進展が示されています。実務では「人間の創作性の有無」「混同防止」を中心に、社内ルールのアップデートが推奨されます。
こうした新しい著作権・商標リスクを正しく理解した上で、安全に生成AIを活用したい方は、
生成AIセミナーおすすめで体系的に学ぶのが効果的です。
まとめ:安全なAI活用のための行動指針
2025年春の大流行は、多くの人にとって生成AIの可能性を実感する貴重な体験でした。一方で、AI著作権問題の複雑さと、適切な知識の重要性も浮き彫りになりました。
今すぐ実践すべき重要ポイント
1. 過去の見直しと今後の方針転換
- 2025年春に作成した画像の使用状況確認
- 「○○風で」などの特定スタイル指定の停止
- 「ツール論」に基づく著作権主張の見直し
2. 体系的な知識習得
- 生成AIに関する総合的なリテラシーの向上
- AI著作権問題を含む法的課題の包括的理解
- 継続的な法的動向の把握
3. 実践的な対策実装
- 事前チェックリストの導入
- 適切なクレジット表記の実施
- 責任分散を考慮したワークフロー構築
法制度は技術の発展に応じて継続的に変化していきます。「あの時はみんなやってたから大丈夫だと思った」では済まされない時代において、定期的な情報更新と専門的な学習機会の活用が不可欠です。
2025年春の流行は確かに楽しい体験でした。しかし、我々がその経験を教訓として、今度は安全で適切なAI活用を実践していくことが大切です。適切な知識と慎重な運用により、AI技術の可能性を安全に引き出していくことができるのです。
※当ブログについて
当サイト「自己啓発ナビ」のプロフィール画像は、生成AIを使用して作成し、その後手動で調整を加えたものです。作成時には特定の著作物を指定する指示は使用せず、一般的なアバター生成サービスの利用規約に従って制作しております。